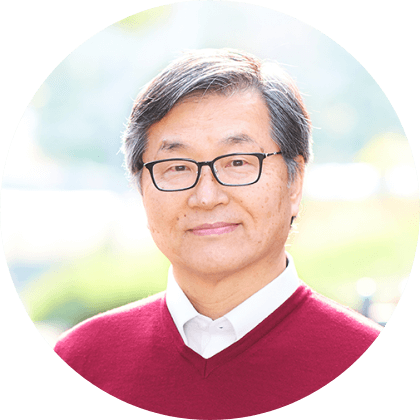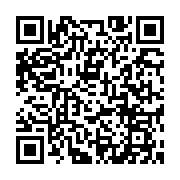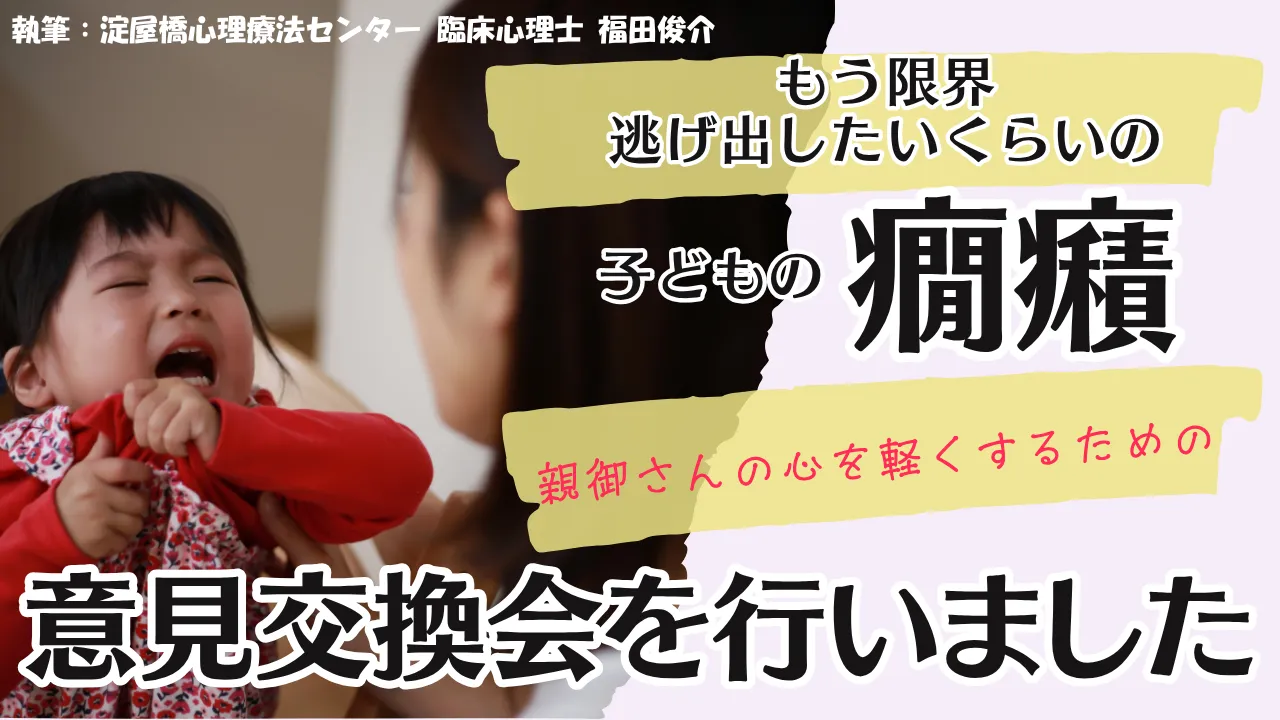
令和7年9月8日(月)【もう限界 逃げ出したいくらいの子どもの癇癪 親御さんの心を軽くするための意見交換会】を開催しました。
この日は、親御さん同士が円になって自己紹介をしていただくところから始まりました。
皆さん、お子さんの困っている様子や日常の悩みを率直にお話しくださいました。
お一人が話し終えるたびに拍手が起こり、「よくお越しくださいました」と声をかけ合ううちに、会場の雰囲気はだんだんと温かくなっていきました。
本記事は、淀屋橋心理療法センター 臨床心理士・福田俊介が執筆しました。
激しい癇癪を起こす小学生の事例

最初にご紹介したのは、とても激しい癇癪を起こす小学校3年生の女の子の事例でした。
発達障害グレーゾーンで、学校ではとても大人しく「いい子」と言われる一方、家庭では夜中に泣き叫び、激しいほどの癇癪を起こしてしまうことがありました。
「甘やかしてはいけない」と親御さんが厳しく接すれば接するほど、癇癪はますますエスカレートしていったのです。
深夜に「今からお菓子を買ってこい!」とご両親に訴え、「今は遅いから明日にしようね」と優しく伝えても納得せず、近所迷惑になるほど大声で泣き叫ぶため、やむを得ずご両親がコンビニまで買いに行くこともありました。
せっかくチョコレートを買っても「ありがとう」とも言わないでフンとぶんどる。
そんな状態が続いていました。
カウンセラーのアドバイスにより、親御さんには続けていた厳しい躾(しつけ)を一旦やめて、お子さんの性格に合った対応を取っていただくことになりました。
その結果、少しずつ彼女の癇癪は落ち着いていきました。
ところが、お子さんの状態が良くなってくると、親御さんの気持ちはゆるむものです。
元々しつけたいという気持ちが強かった親御さんは、再び「しつけ直し」を始めました。
その途端、彼女は手を長時間何度も洗うようになり、夜中に悪夢でうなされるようになりました。
教育的に「しつける」ことが逆効果になるお子さんもいます。
この勉強会では、そうしたタイプのお子さんにどのように関われば良いかを中心にお話ししました。
発達障害のグレーゾーンとは?発達障害の子どもの特徴や対応|発達支援(カウンセリング)をご紹介
カウンセラーからのアドバイス(一部抜粋)
① 癇癪を起こしている最中に、すぐに静める魔法の言葉はありません。
それよりも、お子さんが落ち着いている時の雑談を大切にしましょう。
そうすることで、癇癪そのものの頻度が減っていきます。
雑談では、親よりもお子さんの方が口数が多い必要があります。
いかにお子さんの口数を増やすかは当センターの得意分野です。
平穏な時の親子の関係が深まっていくことが大事なのです。
② 激しい癇癪を起こすお子さんは、とても敏感です。
小さな間違いをいちいち正す必要はありません。
たとえばお店で、「あのピンクのコップ欲しいな」と言った時に、
「あれはどちらかというと紫だよ」と直す必要はないのです。
“受け止める”姿勢が、安心感を生みます。
Q&Aコーナー
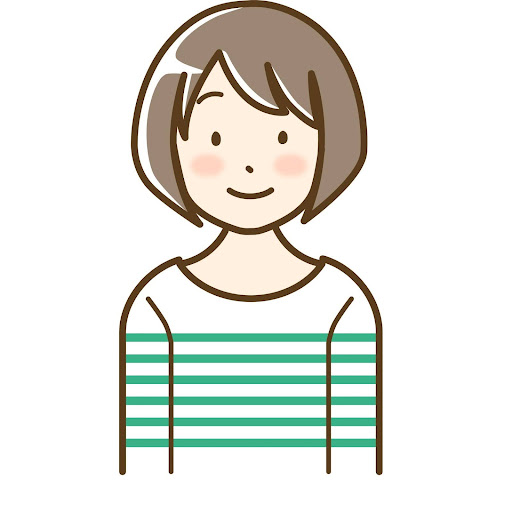
Q1. 子どもが「お母さん、お母さん」と常にくっついてきて、母子密着状態です。どうすればいいですか?

A. 当センターでは、多くの場合「母子密着」をむしろ肯定的に捉えています。 距離が近いからこそ、会話が活性化し、深い話ができるチャンスにもなります。 お子さんが安心して自分の気持ちを主張できるようになると、次第に癇癪が減り、自らの力で親から離れ、自立へと向かっていくのです。
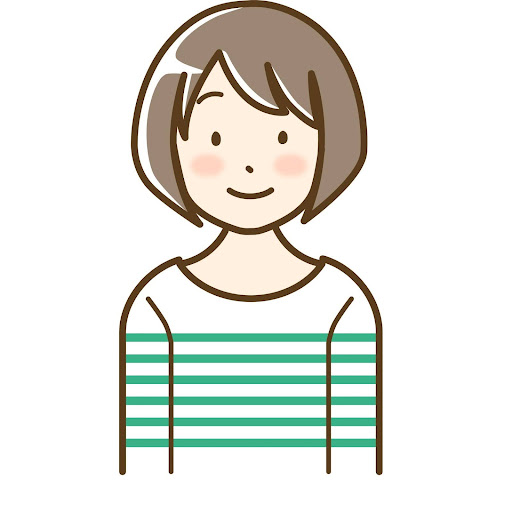
Q2. 「ママ、どう思う?」とよく聞いてくるのに、答えると不機嫌になります。どう対応したら?

A. 「ママどう思う?」という言葉は、意見を求めているというよりも「ママ、聞いてよ」や「ママこっち向いて」といった挨拶に近いことが多いです。 お母さんとつながりたい気持ちはあるものの、実際には答えを求めていない場合も多いのです。答えを出さず、「どうかなぁ?」と言って、あげるだけで満足するお子さんが多いです。
座談会と参加者の声

勉強会終了後には、参加者の皆さんと当センタースタッフが一緒に座談会を行いました。
「兄弟げんかの止め方」や「どちらを叱ればいいのか」など、ご家庭でのリアルな悩みを共有しながら笑いの絶えない時間となりました。
アンケートには、「とても勉強になりました。早く家に帰って子どもと話したいです」
といった嬉しいコメントをいただき、スタッフ一同とても励まされました。
最後に

我々カウンセラーは、解決に向けて親御さんに”伴走”します。
参加された方の中には、「これまで他の機関にも相談したけれど、1〜2回の面談で終わってしまい、心細かった」と話される方もいらっしゃいました。
当センターでは、解決するまで親御さんとともに歩み続けます。
お子さんの変化を焦らず見守りながら、長期的に支えていくことを大切にしています。
子どもの癇癪(かんしゃく)
子どもの癇癪(かんしゃく)とは?癇癪の原因と効果的な対応発達障害との関係性は?相談先一覧紹介
たたく・ひっかく・暴れる・小学生の激しい癇癪で子育てが限界…親が知っておきたい対応法