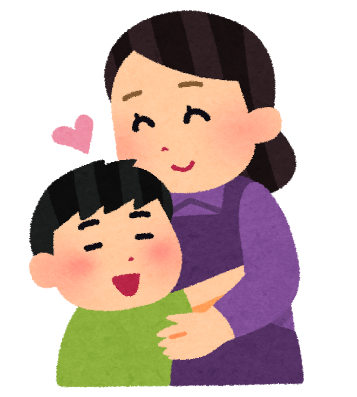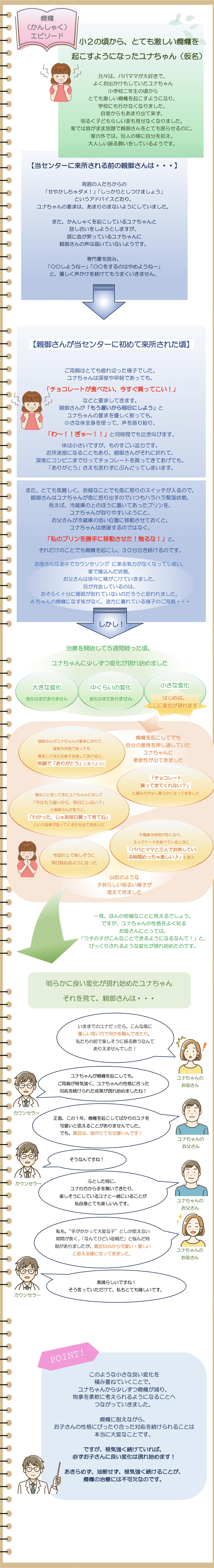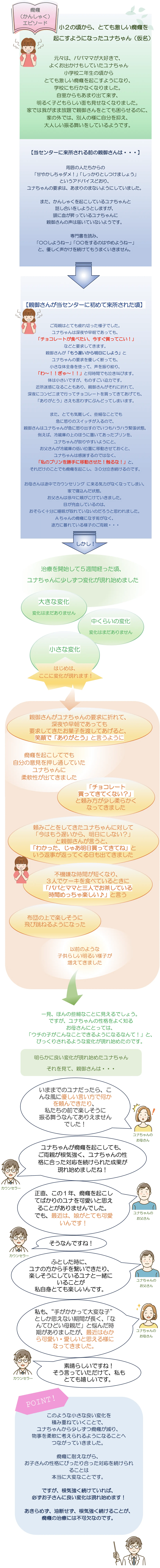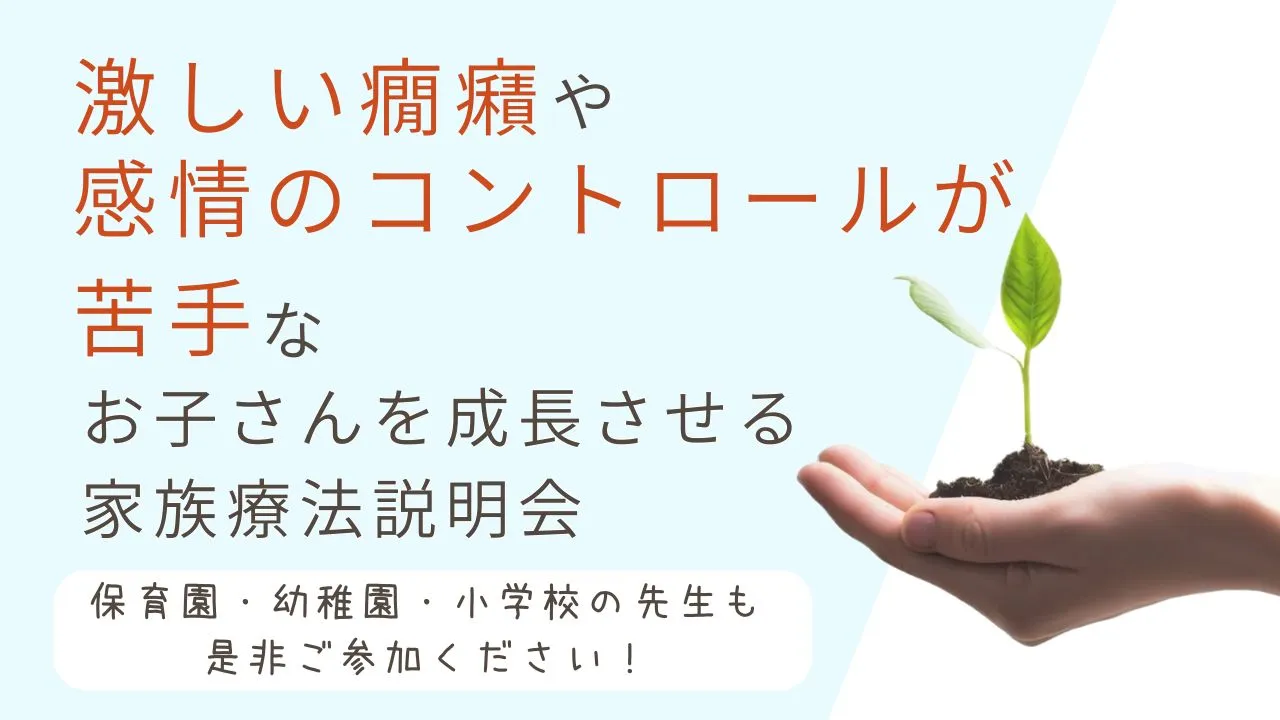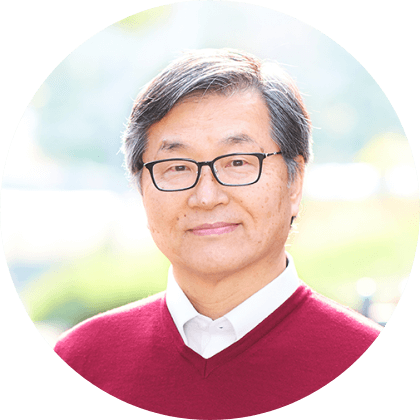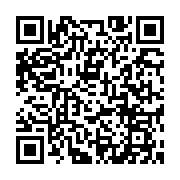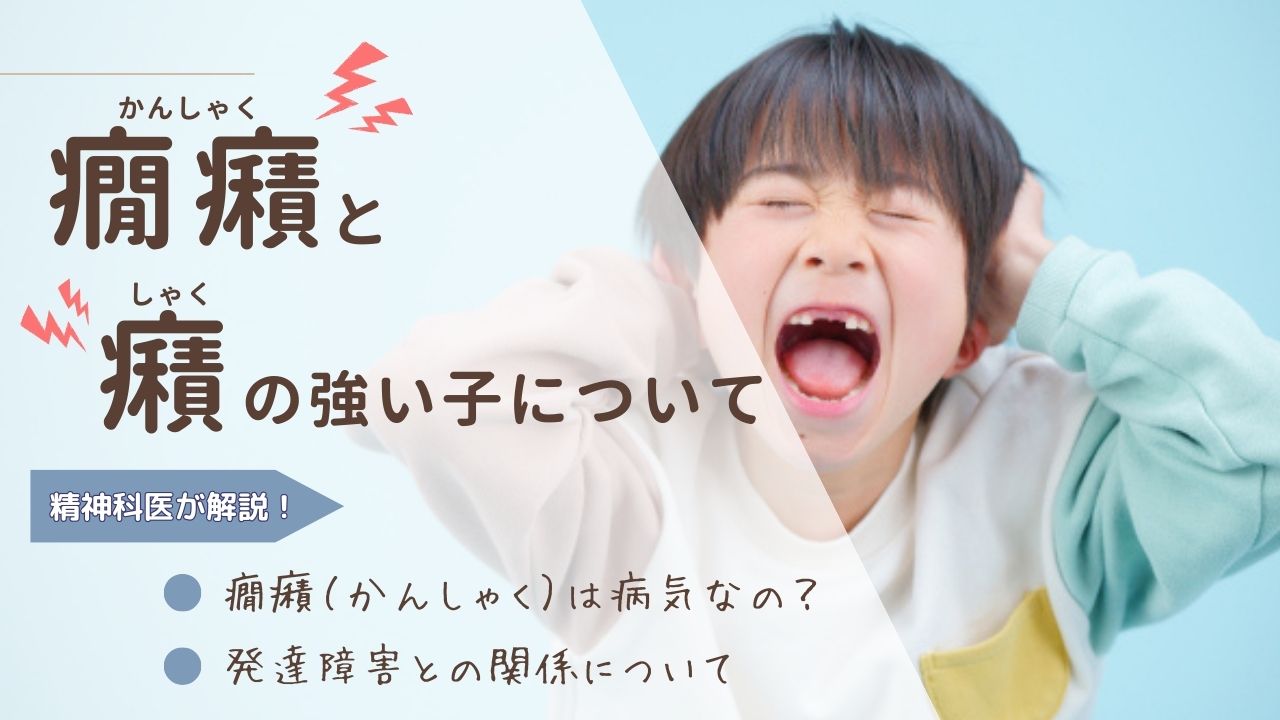
子どものかんしゃくとは、子どもが強い怒りやイライラを制御できずに爆発させる激しい行動や感情の事を指します。

このようなことでお困りではありませんか?

- 欲しいものが手に入らないと、親に買ってもらうまで床を転げまわり、泣き続ける。
- 「今すぐ」これがしたいけど、「今すぐ」にできないと叫んだり、泣き続ける。
- 友達が持っているものを欲しがり、同じものを手に入れるまで「あれが欲しい」と怒り、泣き続ける。
- うまく言い返せないと、顔面が高潮し、物を投げたり手を出してくる。
- こだわりが強く、外出時や登校時「この服は嫌だ、あの靴下は嫌だ」と服装が決まらずに泣き続け、親は毎回遅刻しないかハラハラする。

困り果てた、お父さんやお母さん
子どもが毎日のように癇癪(かんしゃく)を起こし、疲れ切っておられる親御さんがたくさんいらっしゃいます。
子どもが家以外の場所では大人しかったり、良い子の場合、癇癪を起こした時の激しさを周囲の人に理解してもらえない辛さもあります。小さな子どもでも激しい癇癪を起こすと、金切り声をあげて叫ぶ、殴る蹴るなどといったすごい迫力…!!
「最近子供が可愛いと思えなくなってしまって…」
そう涙ぐむお母さんは少なくありません。
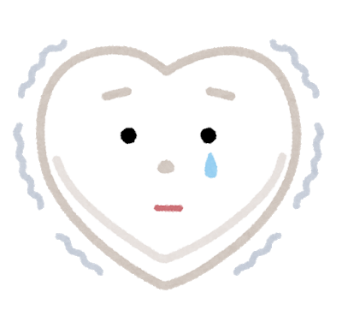
激しい癇癪を起こす子どもへの対応は難しい
- 注意すると余計に荒れてしまう。
- 欲求に答えないと、子どもはしつこく荒れ続けてしまうが、かといって毎日子どもの思い通りにすることは親として出来ないし、したくないと思っている。
- 子どもと話し合いをして納得(理解)させようとするが、うまくいかないことが多い。
- 本や勉強会などを通じ、癇癪を持つ子どもへの対応法を学んでいても、親が精神的にキツくなってくると冷静な対応が出来なくなってしまう。
当センターの方針
お子さんの来所は不要です。お父様かお母様に来所していただき、お子さんに対してどう対応していけば良いのかという具体的なアドバイスをお出し致します。
お子さんが初対面のカウンセラーに対し、信頼して話ができるようになるまでには時間がかかる場合があります。たまに会うカウンセラーがお子さんを成長させようとするよりも、毎日お子さんと接している親御さんに、お子さんへの対応を工夫してもらったほうが有効であることが多いのです。
お子さんが、お子さん自身の言葉で表現する力を徹底的に伸ばすことにより、親に対して癇癪とは違う方法でコミュニケーションが取れるようになります。また、表現する力を持ち、コミュニケーションが取れるようになると、親に対して様々なことを吐き出せるようになるため、家の外(学校など)から持って帰ってくる不満を減らすことができます。
目の前の癇癪だけを治すわけではなく、お子さんを成長させるためのお手伝いをしております。

癇癪を乗り越えた先には…
- 荒れる時間が短くなる、荒れること自体なくなる。
- こだわりが緩くなり、お子さんが「まあいいか」と思える場面が増える
- コミュニケーション能力(交渉力)が付いたことにより、「もういい…」と拗ねることが減り、今後の人生において様々な機会を逃すことが少なくなる。(経験のチャンスが増える!)
- 癇癪が改善されると夜驚症がなくなった、というケースも多い。
その日のストレスを、その日のうちに言葉で表現できるようになったことが影響していると思われる。 - 当初の目的である癇癪の改善という枠を超え、日常生活においてたくさんの成長が見られる。
- 人の気持ちがわかるようになり、兄弟や友人との付き合い方が上手になる。
- 表現力が高まる事により、友達と揉めても自分の力で解決ができるようになる。
- 精神的に安定するようになり、親を振り回す事が減る。
- 好きな事を一生懸命頑張れるようになることで、その他の意欲も高まる。
(親のお手伝いができるようになる、など)
「最近、子供が可愛くて」
困難を乗り越えた多くの親御さんが、笑顔でこのようにおっしゃっています。