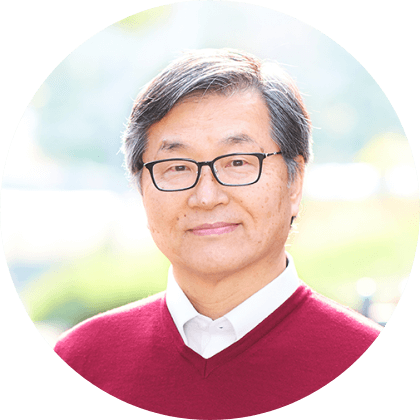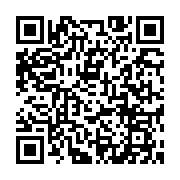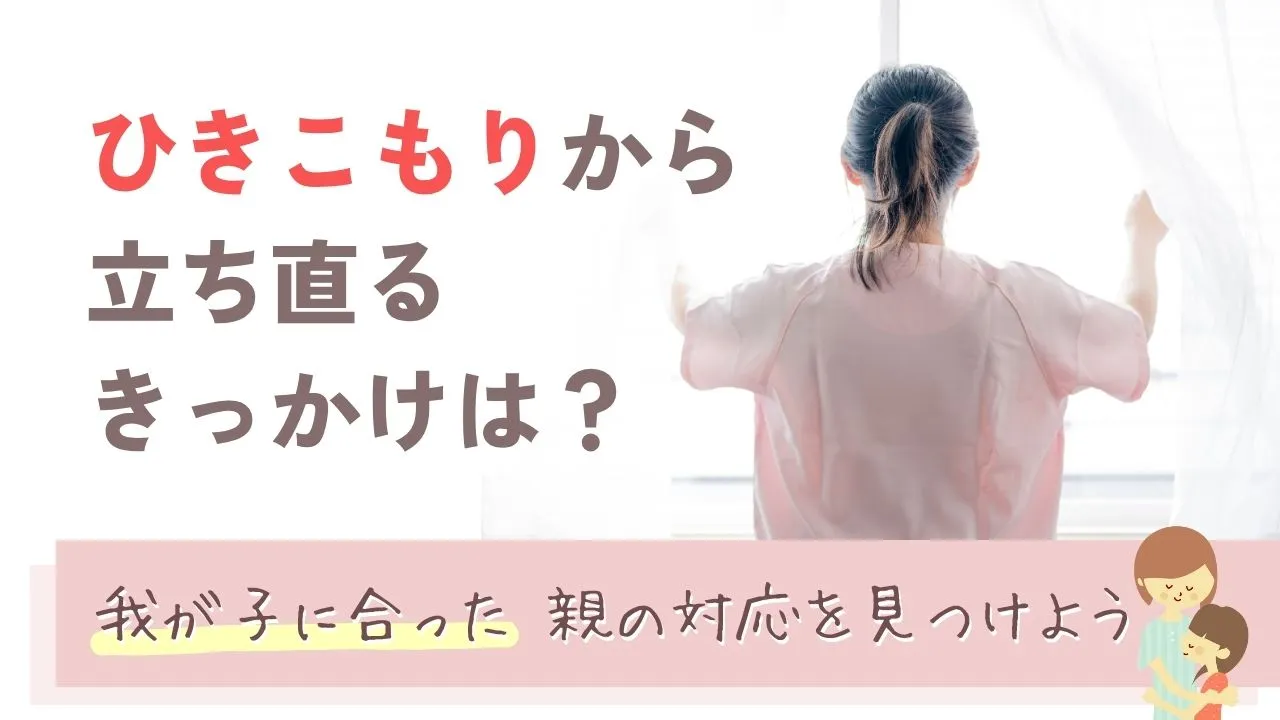
『良かれと思って』かけた言葉が、かえってひきこもりのお子さんの心を閉ざしてしまう……。そんなご経験がおありではないでしょうか。
うまくいかない理由としては、
- お子さんにあった対応ができていない
- お子さんと親御さんの相性が噛み合っていない
こういった理由が考えられます。
この記事では、お子さんにあった対応とは何か?その理由や具体的な対応をお伝えするとともに、スタッフによるひきこもり治療説明会のレポートをお届けいたします。
ひきこもりのお子さんが立ち直るきっかけは、親御さんとの会話の中にあります。ぜひご参考にしてください。
※この記事は、2025年6月17日に淀屋橋心理療法センターで行われたひきこもり治療説明会を基に執筆しております。
目次
ひきこもっている子どもに届かない「良かれと思って」の親の対応
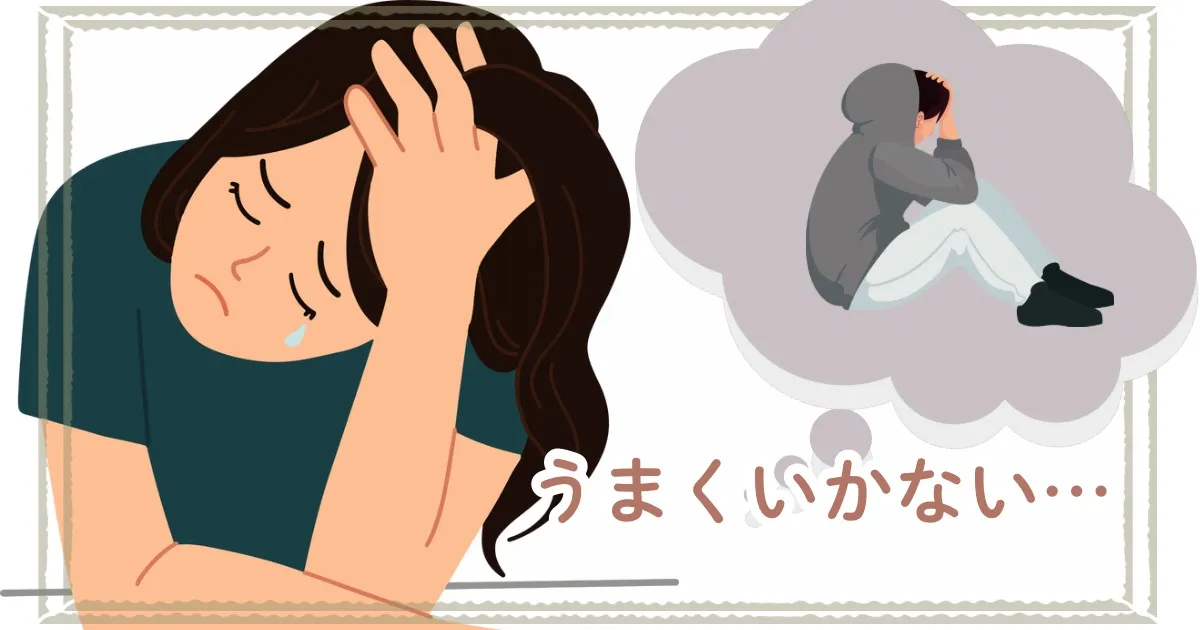
子どもにもっと話しかけなければと、親御さんの多くは、ひきこもるお子さんと一生懸命に関わろうとされます。
しかし、お子さんによっては、積極的な関わり方で必ずしも良い方向に向かうとは限りません。
- お子さんがどのような性格か、親御さんは見極めておられるでしょうか。
- 親御さんご自身は、どのような性格でしょうか。
この章では、ケース紹介で臨床心理士・福田俊介が述べた対応のコツを、「2つのなぜ?」の視点で考えてみましょう。
なぜ「たくさんの質問」は逆効果なのか?
1つ目のケース紹介では、親子の会話がまったくないケースが紹介されました。ひきこもりの20代の男性は、たまに喋っても「イチゴ」、「ミルク」のような単語のみ。
カウンセラーのアドバイスは、シンプルかつ意外でした。
- 子どもが発した言葉は全てメモする。
- 声かけの回数を減らす。
- 質問を減らす。

「質問しないと、会話が減ってしまうのでは……?」
親御さんのこれまでの対応と真逆ですから、当然不安になりますよね。実は、筆者も同じ考えだったので驚きました。
子どもに良い傾向が見られると、つい声をかけたり前のめりで質問したり、多くを子どもに求めがちなタイプだったからです。
しかし、このケースの場合には、そのような積極的な声かけは逆効果であると、臨床心理士・福田俊介は言いました。
お子さんによっては、質問されることがしんどい場合があります。質問されると「答えなきゃ、答えなきゃ………」と焦るあまり、徐々に心に負荷がかかっていくからです。
ですので、親御さんとしては、働きかけたいのをグッと我慢する、押してダメな場合には引いてみる、こういった地道な対応を継続することが求められるのです。
なぜ「その子にあった対応」が必要なのか?
治療説明会で語られた、もうひとつのケースをご紹介します。
ある程度会話ができるお子さんのケースです。カウンセラーからのアドバイスは、ここでも非常にシンプルなものでした。
- 会話の主導権を、子どもに持たせてあげる。
- 子どもの次の言葉を、じっと待つ。
- 返事は、いつもより短めに。
お子さんとコミニュケーションを取りたい親御さんにとって、上記のことは簡単ではありません。
そんな親御さんが、お子さんに会話の主導権を持たせてあげるなどのアドバイスを地道に実践し、お子さんに少しずつ主体性や自主性が芽生え始めた頃……。
親御さんの油断
以前の親御さんが主導権を持った会話に、対応が戻ってしまった。その途端、お子さんの成長もぴたりと止まった。
臨床心理士・福田俊介によると、お子さんが良くなると親御さんが油断し、対応が戻ってしまうのはよくあることだそうです。
このケースでは、お子さんの成長が止まってしまったことから、多弁な関わり方は「あっていない対応」だとわかりました。
では、なぜその子にあった対応が必要なのでしょうか。ポイントは、
親御さんの性格が良い・悪いという話ではなく、あくまで「相性」の問題です。例えば、せっかちなお子さんには、せっかちな親御さんの方がうまくいくこともあれば、その逆もあるそうです。
「なんだか会話がうまくいかないな」と感じることがある場合は、親子の相性が合っていないのかもしれません。
当センターでは、細かな会話記録をお願いして、お子さんひとり一人の性格を見極めます。
そういったカウンセリングを得意としています。
【Q&Aより】「ゲームの話」や「批判」を止めない

臨床心理士・福田俊介と、精神科医・福田俊一によるQ&Aの中から、印象的だったご質問をいくつか紹介します。
Q.親がゲームに詳しくないので何を話せばよいかわからない
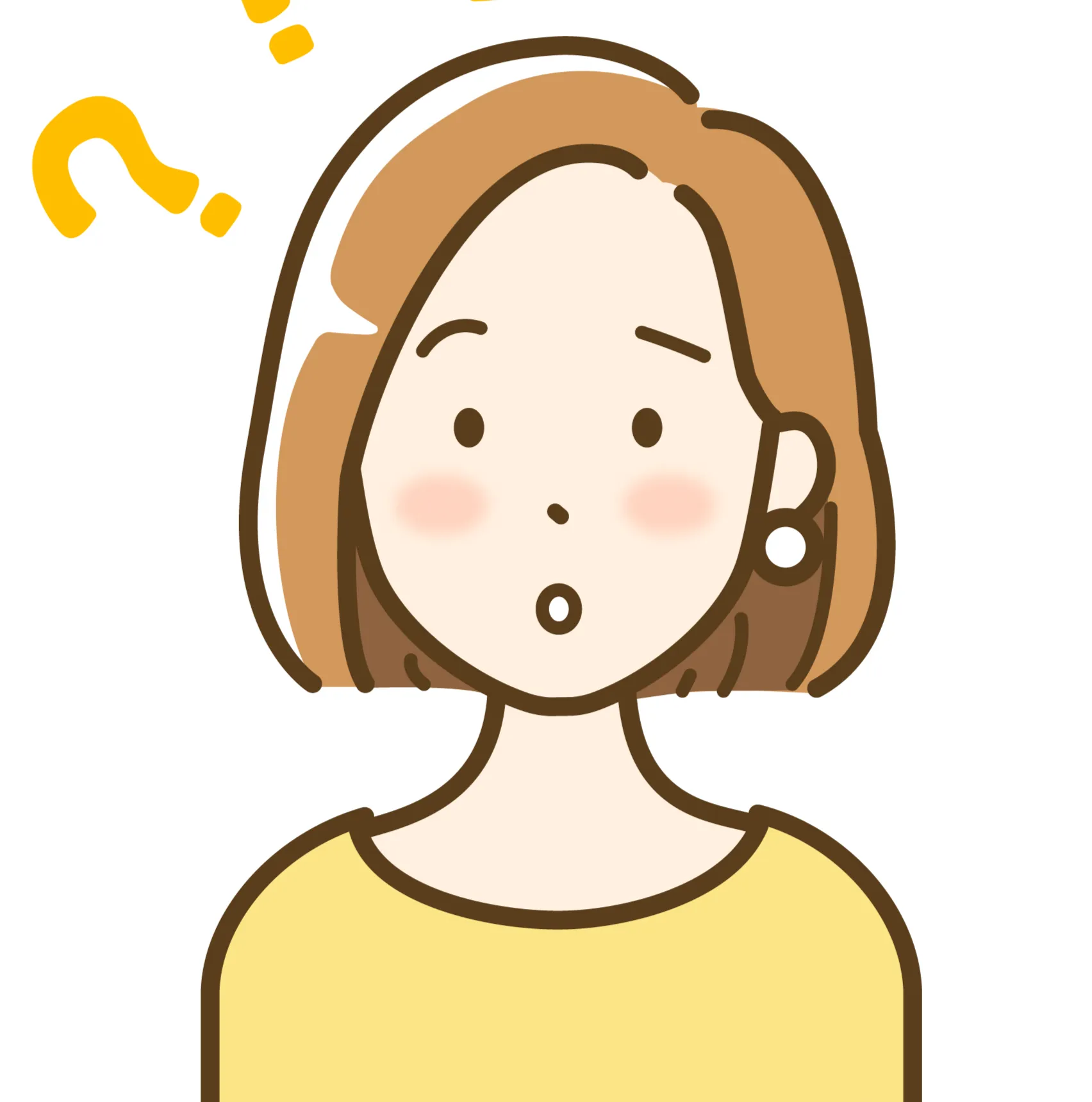
私はゲームに全く詳しくありません。子どもからゲームの話をされた時は、どうすればよいでしょうか?また、子どもといっしょにゲームをしたほうがいいでしょうか?

いっしょにゲームできたほうがいいですが、どうしても興味を持てなければ仕方ありません。もしお子さんがゲームの話をしてきたら、『へえ、すごいね!』、『それでどうなったの!?』と、興味があるように聞いてあげてください。
臨床心理士・福田俊介の回答は、とても意外でした。ゲームに詳しくないと、子どもにしてあげられることはないと思いがちです。筆者もそう思っていたため、ゲームの話をされると気のない返事ばかりしていました…。
親側にとって大切なことは、話す内容ではなく、「あなたの話をしっかり聴いているよ」と子どもに伝わることなのだと思い直しました。
Q.息子と父親(夫)の関係性があまり良くない場合はどうしたらいいか?

夫が息子に厳しい対応をとります。ひきこもっている状態を甘えではないかと考えているようで、スマホやゲームを取り上げて罰を与えようとします。

A.この状況をなんとかするとしたら、やり方は2通りあります。
- 厳しくすることは、「この子の場合には」裏目に出る対応だと伝える
- 父親の厳しさを逆手にとって「利用」する
淀屋橋心理療法センターの所長であり精神科医・福田俊一は、正反対の対応策を2つお伝えしました。
それぞれ説明する中で、親御さんにかけられた言葉がとても心に残っているので、紹介させていただきます。

①厳しい対応が間違っているわけではなくて、その子の性格にあっていないよ、と伝えることです。そのためには、いくつかのエピソードを加えて説明してあげると効果があるかもしれません。
具体的には、
- お子さんが大笑いした時
- 厳しい対応で口をきかなくなったなど、対応が裏目に出た時
などのエピソードをお母さんが書き留めておき、集めたエピソードからご主人に判断してもらいましょう。
また、次の言葉も印象的でした。
笑ったり怒ったりする姿は矛盾したものではなく、その子を構成するピース。だからこそ、子ども一人ひとりにあった関わりが大切なのだと、改めて気づかされます。
次に、2つ目の方法で印象的だった内容をお伝えします。

②母親との会話の中でどんどん伸びる芽があれば、父親の理解が全く進まなくてもなんとかなります。お父さんの批判を通じて、「批判力」を鍛えましょう。
続けていくうちに、自分の意見を言うなど、しゃべり方が変化していきます。子どもの自主性は、しゃべりに表れるのです。
偏った状態ですが、そのまま伸ばしていくと、しばらくしてから「あれ?オレ今何してるんだろう……」と自分の状態に気付き、やがて自ら立ち上がろうとする時が来ると言います。
子どもから批判や否定的な発言を聞くと、親は「良くないことだ」と思いがちです。しかし、決してそうではないとわかりました。
批判も成長過程のひとつとして、自主性の芽と捉える。その芽を摘んでしまわないよう、子どもの小さな変化に気付こうとする親の努力が重要なのだと感じました。
【スタッフより】治療説明会の「ココ!」を伝えたい
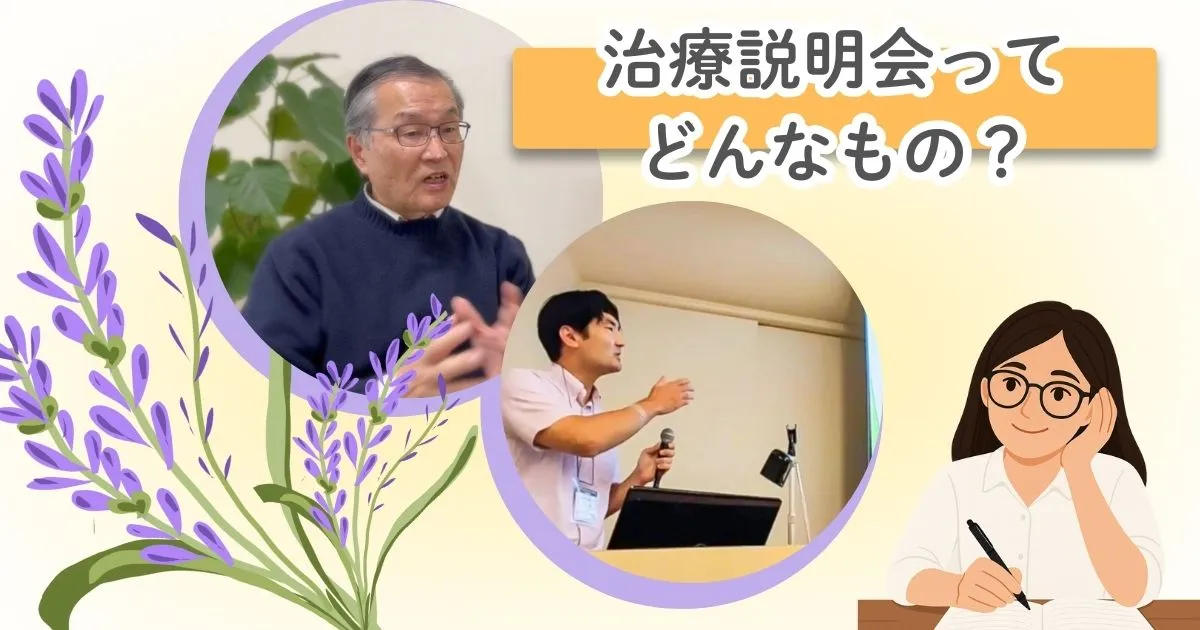
最後に、淀屋橋心理療法センターの治療説明会の空気感や進行の様子などをお伝えします。
治療説明会に興味を持っていただいた方に向けて、当センターの「パワー!」をお届けできたら嬉しいです。
【プロローグ】臨床心理士・福田俊介の問いかけ
「皆さんのお子さんは、柔軟な考え方をされていますか?」
これは、治療説明会冒頭、当センターの臨床心理士であり講師の福田俊介からいきなり投げかけられた「問い」です。
聴講した筆者も漏れなく「エッ!」と動揺しましたが、問いの後に続く講師の自己紹介で、いっきに場の雰囲気が和んだように思います。
講師・福田俊介が自身の10代を振り返りながら、
「あの時、『もっと柔軟に考えられていたら、他の選択肢に気づけたのになァ』と思うのです……」
と述べた言葉が、頭の片隅に強く残りました。
治療説明会はどんな存在?
当センターの治療説明会は、セミナー形式の一方通行……、ではありません。
臨床心理士・精神科医が参加された方々に質問を投げかけ、コミュニケーションを交わしながら進行するのが特徴です。時には、グループディスカッションを設ける場合もあります。
治療説明会に参加され、少しずつ発言していく中で、緊張がほぐれたり、考えや気持ちが整理されていくこともあるのでしょう。
時折、お話しされるうちに想いが込み上げ、言葉に詰まる方もいらっしゃいます。
参加された方同士で、会話に花が咲く様子もお見かけします。
心に抱えているモヤモヤが、ほんの少しでも晴れる、小さな一歩でも、明日から動いてみようと思える……治療説明会は、そのような場でもあると感じました。
学び、振り返り、これまでの道筋を再確認する場所に
今回新たに印象的だったのは、ある親御さんのご意見です。ケース紹介後に講師とやりとりされ、
- これまで子どもの将来について、随分と思い詰めていた
- 『将来の選択肢はひとつだけではない、たくさんの方法があるんだ』と見通しを少し楽に考えるようにしたら、子どもの状態が良くなってきた
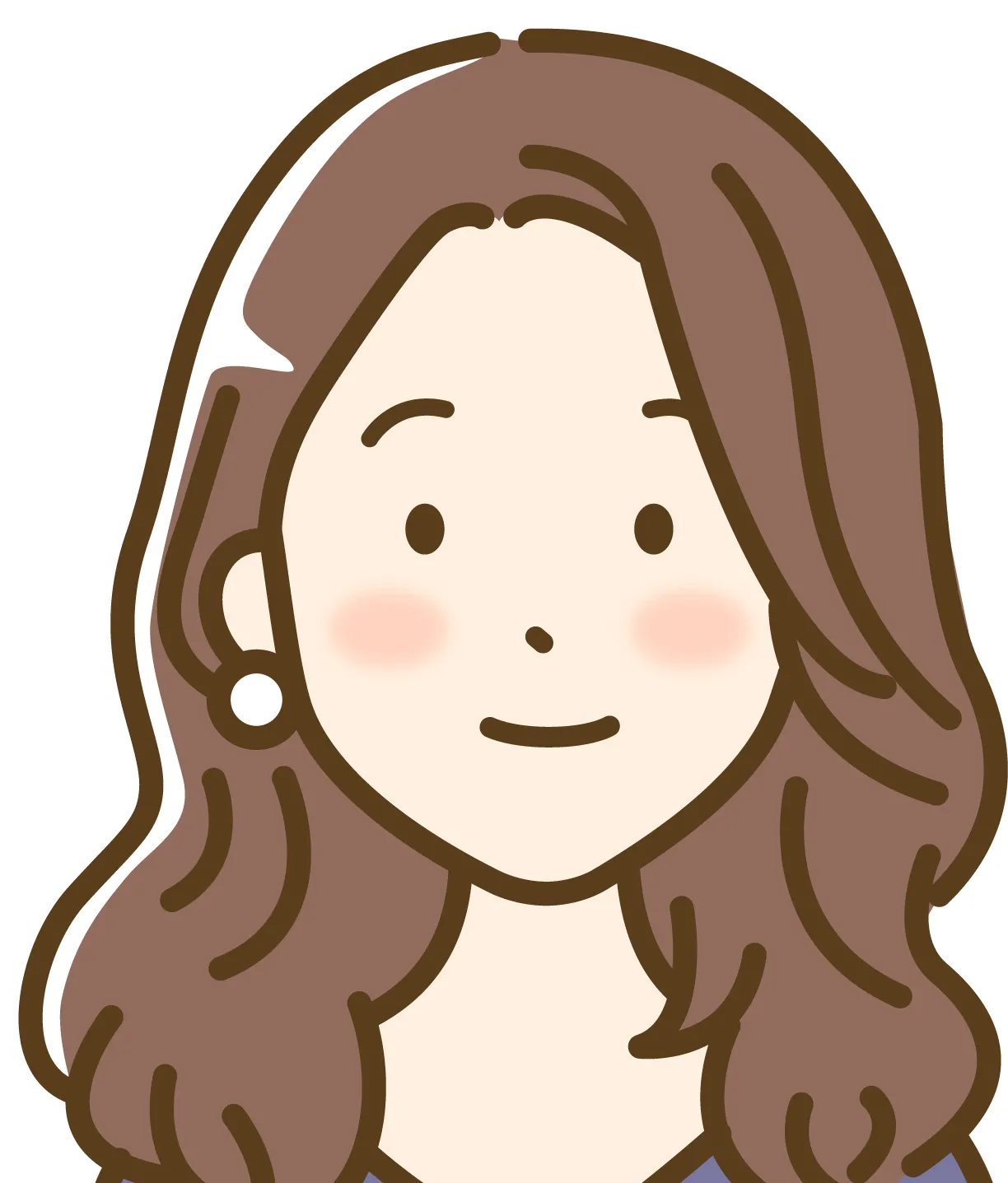
(ケース紹介を聞いて)時間はかかったけれども、子どもにあった対応ができていたのではと考えています
とおっしゃっていました。
当センターの治療説明会には、「解決策を教えてほしい」、「話を聞いてほしい」など、さまざまな思いを抱えた親御さんが来られます。
一方で、今回参加された方のように、これまでの歩みを肯定できる、親御さんひとり一人の想いを受け止められる場でもあると、改めて認識しました。
【エピローグ】臨床心理士・福田俊介のいう「頭の柔らかさ」とは?
改めて筆者がレポートを書きながらケース紹介や質疑応答のやりとりを振り返ると、冒頭で臨床心理士・福田俊介が述べた「柔軟に考えられたらなァ」という言葉が心に刺さります。
さまざまな選択肢を検討できる、柔軟に考えられるということは、自分で解決する力を持っているということだと思います。目の前に大小の壁が現れた時、自力で立ち上がる力がある。そのように捉えています。
当センターのカウンセリングは、会話の中に隠れている小さな変化を見つけ出し、自主性に繋げる。そしてお子さん自身の力で立ち上がれるように伸ばしていきます。
再び困難が訪れても、「自分で立ち上がる力」、「頭の柔らかさ」を持っていれば、もう一度前を向ける。
対症療法的な回復ではなく、根本的に生きる力を育てるから、「綺麗に」治る。これこそが、他の専門機関と一線を画す点であると考えております。
お子さんがひきこもりから立ち直るきっかけは、お子さん自身の中に眠っています。
お子さんの自ら立ち上がる力を信じ、そのために努力を惜しまないと考えておられる親御さんは、ぜひ一度、当センターまでお問合せください。
▶︎ 当センターが初めての方向け
最新の【治療説明会日程】は当センターのホームページから、治療説明会をクリック